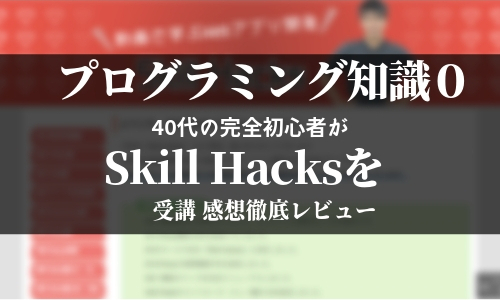昨日も少し紹介したんですが伝えたい所があったのでまた書いてみます
生きていく上で多くの事に繋がっていて、多かれ少なかれ誰しも感じた事があるであろうストレス
そのストレスとどうやればうまく付き合っていけるのか?解消法はあるのか?など「スタンフォードのストレスを力に変える教科書」とい本を元に考えてみようと思います
ストレスは悪いものではない
考え方を変える
幸せホルモンはストレスホルモン
目次
ストレスとは

ストレスは悪いものではないというと、え?と思われる方も多いかと思います
米国で3万人の成人の動向を8年間という期間にわたり追跡、調査した研究があるので紹介します
事前に「ストレスは健康に害になると信じますか」という質問に答えてもらい、その後、公開されている死亡記録を使って調べた結果はなんと
「ストレスは健康に害になると信じている」と考えていた人の死亡率は43%も高かったようです
一般的にストレスは悪いものだし、このデータを見てもピンと来ないと思います。詳細を説明すると
重度のストレスを受けても「体に悪いと信じてない人」の死亡率は低かったとの事
これは結構、衝撃のデータだと思います
更にひどいストレスを経験してもストレスが害であると信じてなかった人は、
ストレスがほとんど無かったグループと比較しても死亡率は低かったようです
いまだに多くの人がストレスは体に悪いと考えているはずです
ストレスが原因で起こってしまうとされるものは多数あって
腹痛、吐き気、めまい、肩こり、うつ病など
これらはストレスが原因で起こる可能性があるとされていますが、実際ストレスが原因だった場合、考え方で回避できるとしたらどうでしょうか
考え方を変える
プレッシャーを感じ心拍数が上がったり、汗をかいたり、呼吸も乱れる
一般的に緊張している状態では「力が発揮できない」などマイナスのイメージが多いと思います
この考えを変えてみる。例えば
心拍数があがっているのは行動に備えて準備をしていて、呼吸が速くなっても問題はなく、脳により多くの酸素を取り込んでいると。
データではストレス反応は能力を発揮できるように助けてくれるものと
捉えるようになった参加者はストレスや不安が減少し、自信をもてるようになったとのこと
そればかりか、身体的反応まで変わったようです
緊張すれば血管は収縮し様々な問題が起こりますが、ストレスが有用であると考えれるようになると心拍数は上がっているものの、血管は収縮せずリラックスしたままに。
つまりずっと健康状態を維持できていたという事になります。考え方で健康が左右されるかもしれません
幸せホルモンはストレスホルモン

オキシトシン:抱擁ホルモンとか幸せホルモンとか呼ばれているので聞いた事があるかもしれません。人との共感を高め、助けたい支えたいと思わせたりもします
この幸せホルモンと呼ばれているものは、実はストレスホルモンなんです
ストレス反応の一環として下垂体はこのホルモンを分泌し
誰かの助けが必要な時にお互いが助け合うようにしているとの事
人生で困難な時には誰かと一緒にいたいと思わせたりもします
ストレス反応であるオキシトシンは体の色々な部分に働きかけ、心血管系を悪影響から守ったり、心臓の細胞を再生したりしストレスで起こるダメージなども修復します
追跡調査で「人を助けるためにどのくらい時間を費やしたか」という質問をし
その後を調べた結果、死亡記録から経済的惨事や家庭危機など重大なストレスを経験すると死のリスクが30%増加したのですが
「他人を助けるために時間を費やした」人々は死亡の増加が全くなかったようで
ストレスを受けながらでも誰かを助ければ自分のストレスが回復する事が分かりました
最後に
すべては思い込みであり、考え方でストレスはプラスになる
ストレスの活かし方などが詳しく書いてあり、知っておくと今後の人生でかなり役立つと思います
1~2年前のニコ生でメンタリストDaiGoさんが今年一番よかった本みたいな感じで紹介していました。もっと深く知りたい方は本を見てみるといいかもしれません
記憶的には紙の本のがいいらしいのですがkindle(電子書籍)が安くてかさばらないので、個人的には紙よりいいと感じてます
数日前のデジタル手続き法案で行政手続き100%オンライン化を目指すというものが、印鑑業界からの反発で見送りになったというのもありますし、
この手のものも、なかなか広まらないんでしょうね